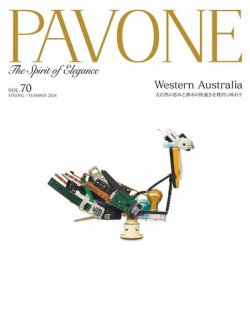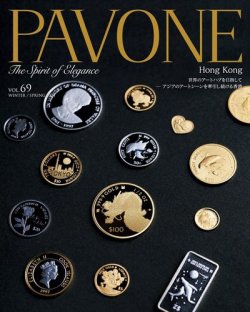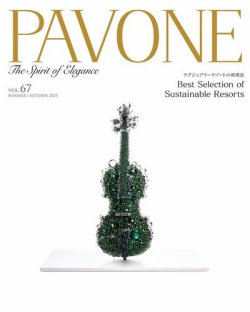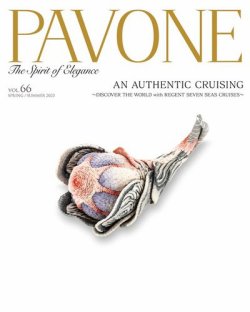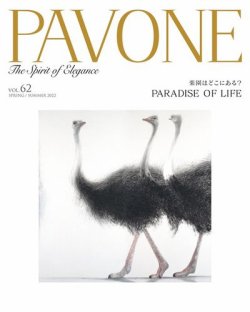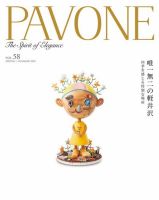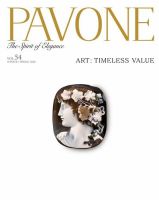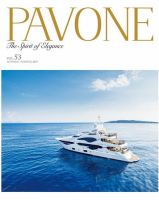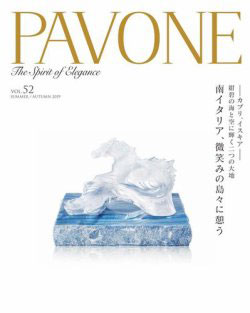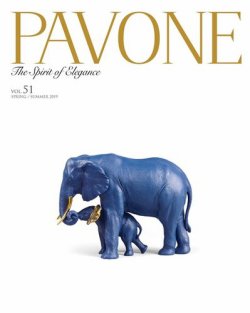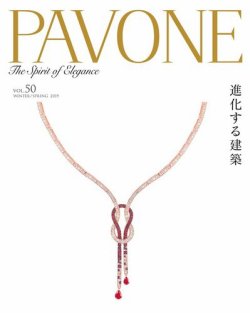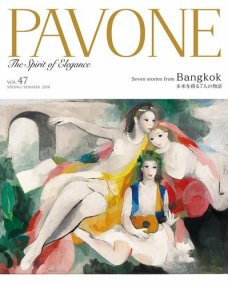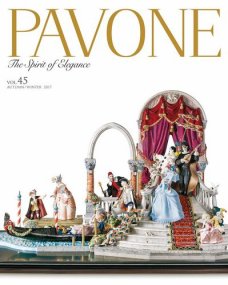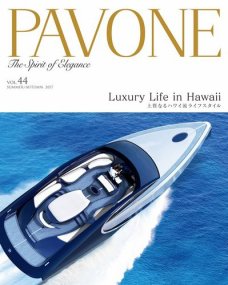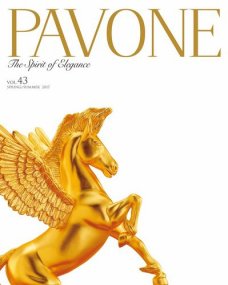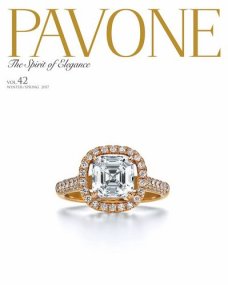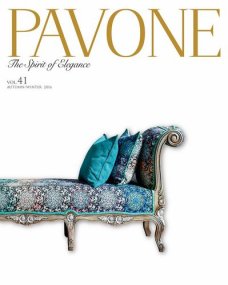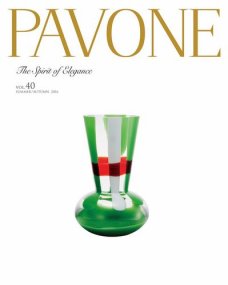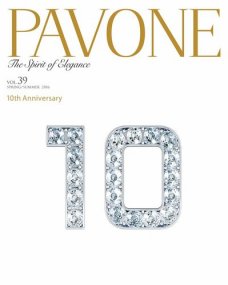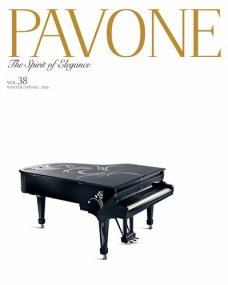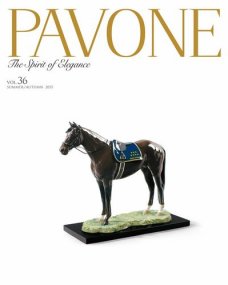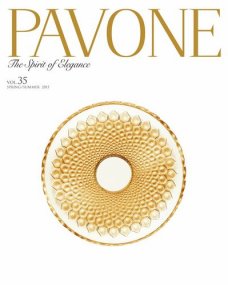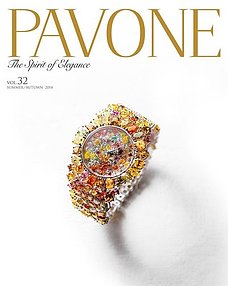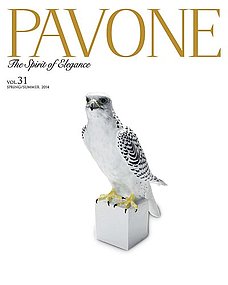那覇空港、某航空会社の出発ラウンジ
ここから眺めは何度見ても美しい。抜けるような青空の下の海、その奥に見える慶良間諸島、空には真っ白な雲がいくつも横たわる。
沖縄での仕事を終え、東京へ帰る飛行機の出発を待つ、つかの間の時間を過ごすラウンジ。
沖縄に定期的に出張するようになって、もう7.8年になる。月に2.3回の割合で訪れ、企業コンサルティング、講演会の講師、そして大学での講師などを1泊2日、長くても2泊3日の間にこなしていく。夏真っ盛りのシーズンの時、観光客であふれかえる飛行機の中で一人スーツを着て、黙々とパソコンをたたき締め切り間近の原稿と格闘している姿は、周りにどのように映っているのだろう。
しかし、このラウンジの中では、ビジネスマンが多く、そんな視線を気にする必要もない。
しばらく前、台風が沖縄に接近しているとのことで、予約していた飛行機の出発が難しい状況だった。夕方のその便が飛ばなければ、その日はもうダメだろうと思えた。出発するかどうかわからないということで、チェックインを済ませ、かのラウンジでしばらく待つことにした。ラウンジは、多くの人でごった返していた。それから数時間…。
どうも飛行機が飛ぶ気配がないと思えたので、翌日朝の飛行機を予約することにした。ラウンジのカウンターで空席状況の確認をし、予約の変更を伝えた。
その時、手続きをしていた女性スタッフが顔をあげて、「あら、お久しぶりです」と、こちらを見てにこやかに微笑んだ。「あっ、この間も…」と返答した。対応がとても爽やかで、そして笑顔が似合う。こうした職業にしてはやや背の低い南国美人という感じの女性だ。
翌日…。その日の夕方から東京での講演会が入っていたので、どうしても帰らねばならなかった。少し、早めに手続きを済ませ、ラウンジで講演会の資料の確認をしていた。昨日の空模様がうそのように、台風の過ぎ去った後の空は、きれいだった。
日本の人口減少と経済の深い関係
今回のテーマは「日本の人口減少は日本経済や不動産にどんな影響を与えるか」というもの。
世界銀行が発表している国別人口増加率のデータはかなりショッキングだ。
日本の人口増加率は1973年にピークを迎え、その後一直線に低下しており、2005年以降はマイナスとなっている(つまり総数の減少)。
生産者人口の減少が始まるのが1995年。この頃から、「人口減少社会が来る」と言われ始めた。
しかし、このデータはかなり以前からの公表データであるから、1970年代後半には、人口減少社会が来るという確信に近い予測はできていた(が、広く公表されなかった)。
こうした事実から、現在の新興国(新興大国)の未来を予測することができる。一人っ子政策をとってきた中国は、確実に経済的に厳しい未来が待っている。
日本では人口増加率減少(1973年)↓バブル崩壊(1990年)の間が約17年。
中国の人口増加率のピークは日本と同時期だが、その後1985年.1989年ごろにかけて再び上昇した。この頃をピークと見ると、今年2011年は1989年から約20年が経過している。
いくつかのデータでは、中国の不動産価格は今年に入り、牽引してきた地域を中心にピークを過ぎて、マイナスに転じているようだ。どうも、危険な香りがする。
日本の人口は、1950年には世界第5位。現在はだいたい10位くらい。あと10年もすれば大きく順位を落としそうな勢いだ。
島国で、他民族に排他的なお国柄である日本の人口動態は、ほとんど自然増減によって決まる。出生数-死亡数で決まるのだ。欧米各国は移民の受け入れなどの社会増減(流入-流出)があり、先進国はプラスが期待される。日本は人口減=出生率減と考えるが、流入を増やすことも一考に価する。GNPだけで経済状況を判断するのは早計であるが、GNP増のためには人口増が不可欠だろう。
一路、東京へ
だいたい話す内容がまとまった。講演には多くの方が集まってくださっているらしい。
さぁ、出発しよう。席を立ったそのとき、昨日の女性が、「おはようございます」と笑顔でこちらを見た。「今日も朝からここの担当です。よくお会いしますね」と言い、名刺を差し出した。「よろしくお願いします」と、お辞儀をした。今まで見た中で、彼女の最高の笑顔だった。
こちらも名刺を取り出し、ボールペンで携帯電話を書いて、手渡した。「いつか、電話くれたら、うれしいな」と付け足した。
ラウンジの出口まで見送られ、とてもすがすがしい気分で飛行機に乗り込んだ。
2時間30分のフライトを経て、飛行機は羽田空港に到着。快適な空の時間だった。
携帯電話を取り出して、メールと留守番電話の確認をする。講演会の主催者からの伝言と、小さな女性の声でメッセージがあった。「先ほどは、ありがとうございました。次回、那覇へお越しの際には食事をご一緒しましょう。連絡をお待ちしております」
その日の講演はとても気分よく、あっという間の90分だった。
彼女の青いスカーフが目に焼きついている。