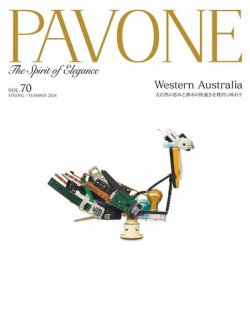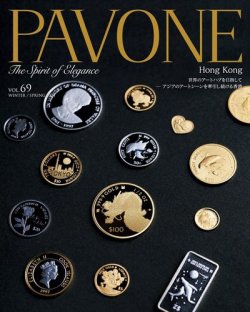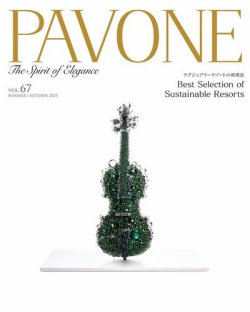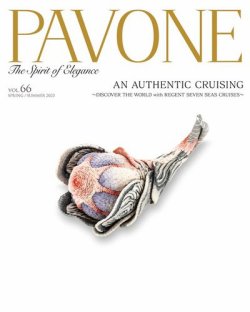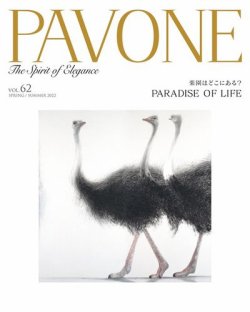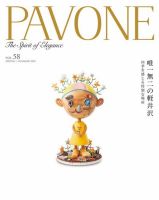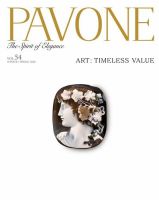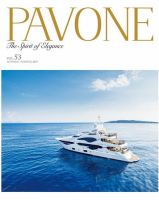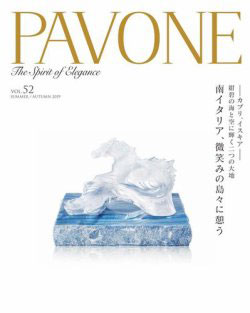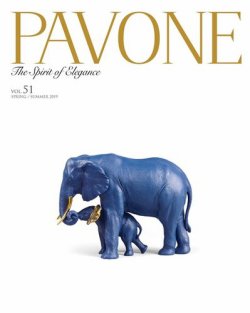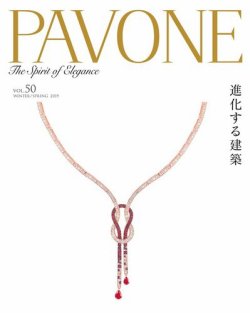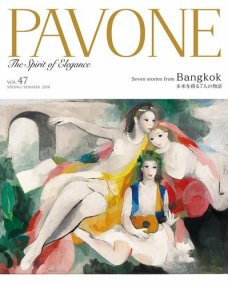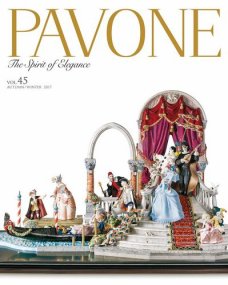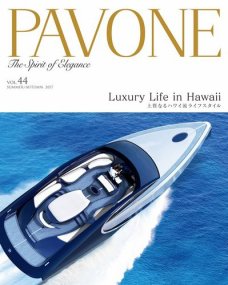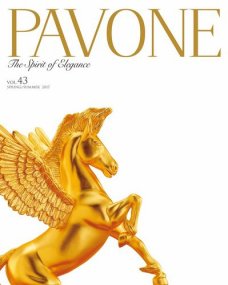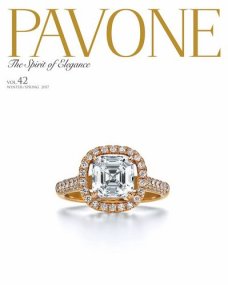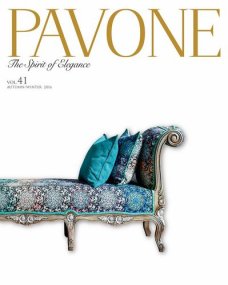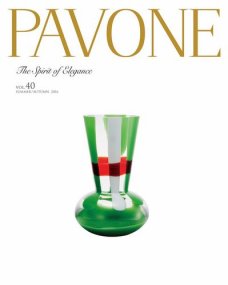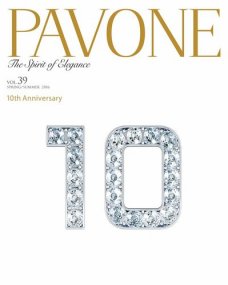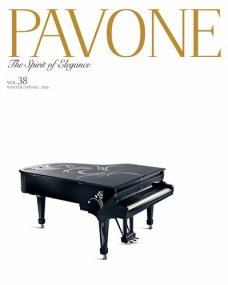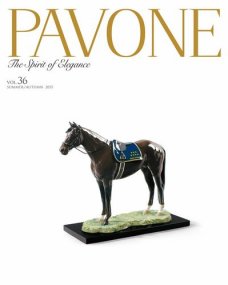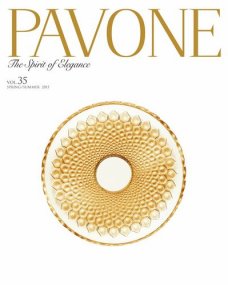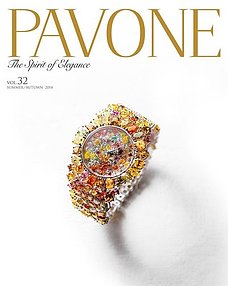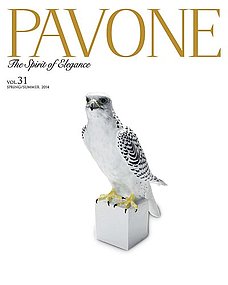ベトナム ホーチミン タンソンニャット国際空港―。
夕方、成田を飛び立った飛行機がこの街に到着するのは、現地時間で21時半をすぎた頃だ。
今日は、ビジネスクラスの席も大半が埋まっていた。かつては、がらんとしていたビジネスクラスのシートも、最近はたいていいつも満席に近い。こんなことからもベトナム経済の勢いを感じる。
飛行機から降りると、南アジア特有のねっとりとした生暖かい空気を感じる。この空気は嫌いじゃない。何とも言えない、解放感と妖艶さを感じるからだ。
入国審査を終えて、エレベータを降り到着ゲートへ向かう。外に出ると、何年ぶりかに出会う素敵な笑顔があった。
「空港まで迎えにいくよ」。
そう言ったのは彼女だった。政府系企業が主催する講演会に招かれることが決まると、そのことを彼女に伝えた。
「へー。ずいぶん偉くなったのね」。おどけた声の時は、ご機嫌の合図だ。
ボクは数年前まで、毎月のようにホーチミンを訪れていた。あるメーカーがこの地に大きな工場を建てて本格的に進出するための市場調査や需要予測などをしていた。そこで通訳として出会ったのが、彼女だった。外資系の航空会社で勤務していたが、大学時代に習得したベトナム語を活かした仕事がしたいと移住したのだ。彼女とはすぐに仲良くなった。
仕事の時間と関係者との会食の時間以外ずっと、彼女と二人で時間をともにした。朝も昼も夜も。実際は仕事でも一緒だったから、文字通り四六時中一緒だった。
一回の訪問は、だいたい7日くらいだった。ボクが帰国する最後の夜はいつもサイゴン川に面したお店に行った。このデッキから見える月は最高に綺麗だった。月を見ながらの時間を過ごし、ボクは23時50分に出発する便に乗るため、慌ただしくタクシーで空港に向う。
「空港まで見送りに来てよ。寂しいからさ」。
「送っていくのはイヤ。絶対泣いちゃうから」。
小さな声だった。
「もう少し、月を見ている」。
そう言ってお店に残った。
「今夜も、あの店に行こうよ」。
空港からのタクシーでそう言った。
「もちろん! リザーブしているよ」。
東京オフィス賃料に上昇のキザシ
明日の講演の資料は飛行機の中で完成させておいた。ボクは、いつも機内食は食べないことにしている。機内では、もっぱら原稿の執筆をしているか、すやすや寝ている。
今回は、東京のオフィスビル市場についての講演を頼まれた。日本の景気が近年回復していることは、世界的に周知の事実となっている。アジア各国の投資ファンドも多くのお金を日本に再び投資し始めている。大きな投資の受け皿となっているのは、東京都心の大きなビルだ。値上がり期待もさることながら、安定した賃料収入の期待も大きい。
TOPIXなど証券市場の指数は、政権が変わり、経済政策の効果が見え始めるとすぐに反応した。しかし、オフィスの賃料の反応は鈍かった。日本企業は、人員採用やオフィスを新たに借りることに慎重だった。好景気がいつまで続くか分からないという不安からだった。
しかし、ここにきて企業は積極行動に舵を切った。そんな傾向から、2014年度が始まってからの東京都心一等地のオフィスビル賃料は上昇し始めた。おそらく、今年の秋には、メディアも騒ぎ始めるだろう。そんな情報をいち早く届けることにした。
あの頃の月
住宅地を抜けて、タクシーはお店の前で止まった。いつものように、Bambooが二人を迎えてくれる。彼女は、川沿いの席をリザーブしてくれていた。
「なつかしいね。あの頃よく食べたものを注文しようよ」。
彼女は流暢なベトナム語でオーダーする。
「3年ぶりだよね。元気にしていた? あなたの活躍は聞いていたよ」。
「もう、結婚したの?」とボクは、おどけて聞いた。
「答えないよ。そんな質問には。そっちこそ、どうなの?」
彼女もおどけた。
赤ワインのボトルを1本開けた。ワインのせいか、久しぶりの再会からか、静かで優しい時間が流れる。
「あなたがこっちに来なくなってから、私は毎日毎日泣いていたのよ。そして、いつもここに来ていた」。
「空を見上げると、月が出ている。あなたも見ているのかな?と思って見ていたんだよ」。
彼女は急にしんみりとした声でそう話した。
ボクは、なんだか切なくなって彼女の手を握った。
「今夜は、部屋においでよ。あの頃のような時間を過ごそう」。
彼女は、にっこり笑って言った。
「もう少し、月を見ている。だってあの頃みたいでしょ」。
ボクは、一人でタクシーに乗った。サイゴン川の水面には、月が映っていた。