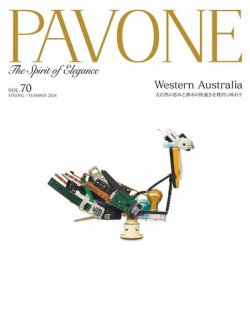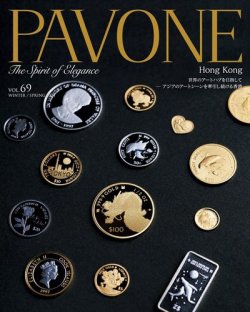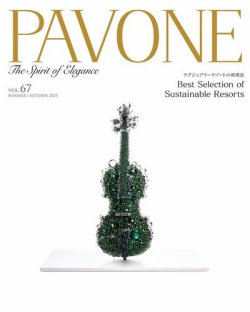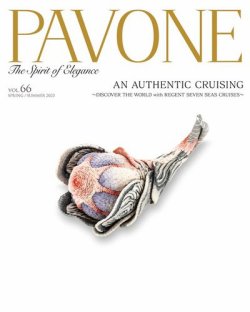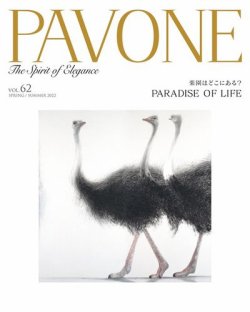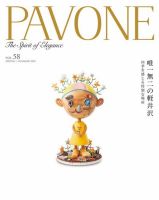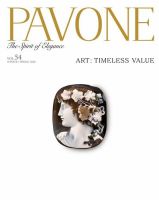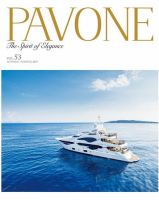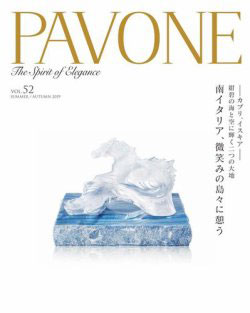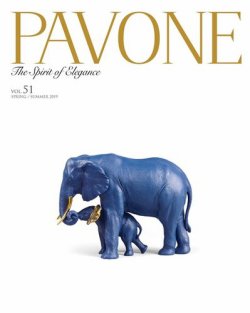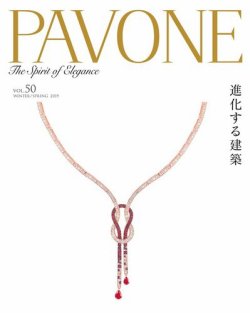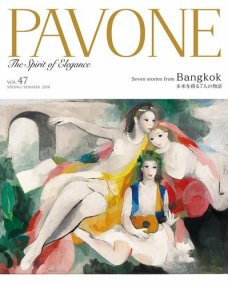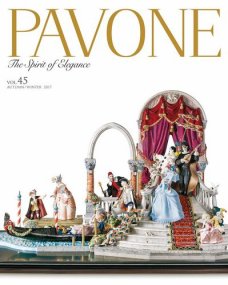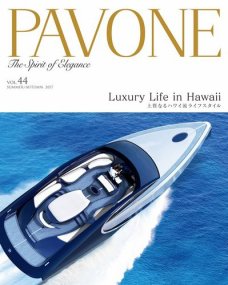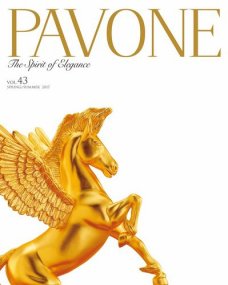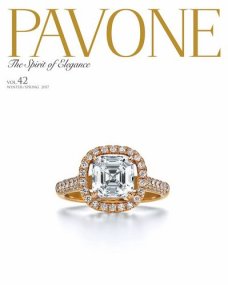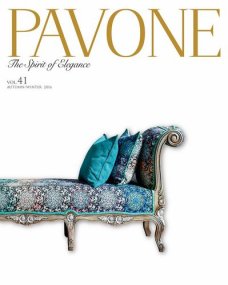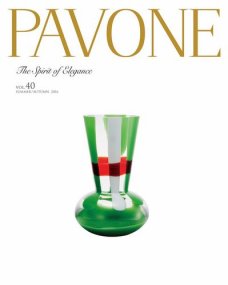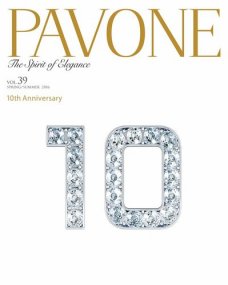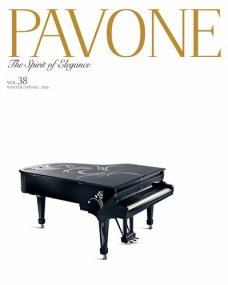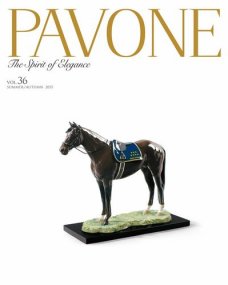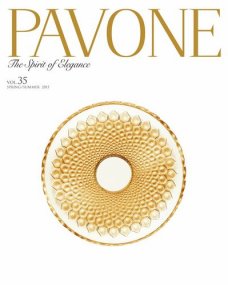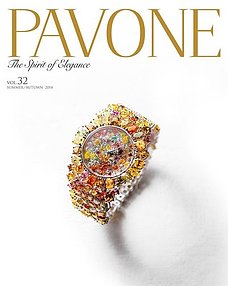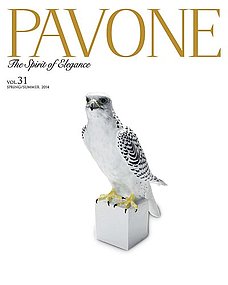京の伝統、その現在進行形。 ~プロジェクトユニット「GO ON」のモノ作り~
「GO ON(ゴオン)」とは京都の伝統工芸に携わる若き後継者たちが集い、受け継がれた「技」と「素材」を駆使して、世界に向けてその可能性を発信する取り組み。
プロジェクトが発足して丸3年目を迎え、京都の伝統工芸は、今という時代のシーンにフィットさせながら、様々な形に昇華している。
新たなマーケットの創出を目指して。京都の若旦那衆たちによる挑戦
京都から世界へ向けて

GO ON/西陣織 細尾 取締役
細尾 真孝さん
パリコレのランウェイを西陣織の煌びやかなスーツが彩り、ロンドンの美術館には京都の小さな工房で作られた茶筒が永久保存される――。近年、日本の伝統工芸が海外で高い評価を得ている。伝統の技術と素材を礎に、既存の枠組みを取り払って、今までにないモノを世に送り出す、そんな試みが実を結び出しているのだ。
仕掛けたのはGO ON。西陣織の「細尾」、竹工芸の「公長齋小菅」、京指物の「中川木工芸」、茶筒の「開化堂」、京金網の「金網つじ」、焼物の「朝日焼」という、京都の老舗伝統工芸の若旦那衆によるグループである。
活動の開始は2012年。10月で丸3年を迎えたが、そもそもGO ONはどのように誕生したのだろう。「着物を例に挙げると、国内でのマーケットは、ここ30年で10分の1に縮小しました。マーケット自体がなくなる細尾家の住まいだった京町屋づくりの家を改装し、GO ONのショールーム「HOUSE of HOSOO」として一般に公開している(要予約)。ことはないにしろ、今後、国内のマーケットが10倍になるとは考えられません。そう考えた時、職人や産地を守るためには、自ら海外に出て、新たにマーケットを作り出すしかない。他の京都の伝統工芸でも、同じ思いを抱いていました。海外への展開を考えて、パリのメゾン・エ・オブジェやミラノサローネに出展した際、隣りのブースにいたのが今のメンバーだったのです。そこで語り合ったのは、伝統工芸が斜陽産業だと思われているが、考え方ややり方次第で成長産業にできるということ。伝統工芸をもっとクリエイティブ産業にしていこうと、意気投合したわけです」。
世界に挑戦するに際し、伝統工芸には「武器」があると自信があった。「日本の伝統工芸が他と差別化できる要素は、例えば西陣織は1200年の歴史を有し、長い間、アッパーな顧客にお誂えの織物を織っていく過程で、技術や素材が磨き上げられたという背景があります。これまで国内だけに目が向いていたという過去は、つまりは世界が知らない技術や素材が手元にあるということ。これはグローバルに見れば大きなチャンスに他なりません。もちろん西陣織に限らず、他の京都の伝統工芸、ひいては日本すべての伝統工芸にいえることです」。

細尾家の住まいだった京町屋づくりの家を改装し、GO ONのショールーム「HOUSE of HOSOO」として一般に公開している(要予約)。
世界に向けて今までにない新しいモノを生み出してきて3年。着実に手応えも感じている。「先ほど伝統工芸をクリエイティブ産業にしたいと申しましたが、その根底には、伝統工芸の職人を子供たちが将来、なりたい職業にしたいとの思いがあります。自分たちの取り組む姿勢で、伝統産業に対する固定観念を変えられると考えました。そんな意味では近頃、多くの若者が伝統工芸の世界に足を踏み入れてくれるようになりました。彼らの共通の認識は、伝統工芸をクリエイティブ産業と見ているということ。自分たちの思いに共感してくれるのは本当に有り難いことだと感じます」。
ところでGO ONでは、メンバー自らが京都の町を案内をするという新たな取り組みにも着手している。「先日開催されたミラノサローネでは、イタリアのダウンジャケットのブランド『タトラス』のショールームで、GO ONのインスタレーションを展開しました。ニューヨークのイベントにも積極的に参加するなど、海外に出て気付いたのが、欧州や北米では〝クラフト=ラグジュアリー〞という文脈が確立されているということ。伝統産業が育まれた京都に対する関心も強く感じていました。それならば、自分たちのネットワークを活かして、一辺倒の旅とは異なる京都を案内しようということに。その取り組みが、『Beyond KYOTO』というプロジェクトです。着物は着物だけでその文化が確立してのではなく、お茶やお花など、様々な文化と関係を持つことで育まれてきました。自分たちの価値を伝えるためには、自分たちのモノの背景にあるストーリーや文化にスポットを当てること、つまり京都の文化を深く紹介することがとても大切なことだと考えています」。
京都に軸足を据え、世界を視野にますます広がるGO ONの展開。先人から継承された価値をリスペクトし、新たな解釈で次世代へ繋げる彼らの取り組みに、これからも目が離せない。
細尾 真孝 Masataka Hosoo
元禄年間(1688年)創業の西陣織の老舗「細尾」取締役。ミュージシャンやジュエリーブランドの商品開発を経験した後、30歳で家業を継ぎ、12代目となる。マテリアルとしての西陣織に着目し、あえて和柄にこだわらない発想で、海外の高級ファッションブランドなどとのビジネスを軌道に乗せる。
西陣織 細尾 ~挑戦を続ける老舗
切り拓かれた、新たな道



椅子の張り地に浮かぶ繊細な柄。西陣織だからこそ
表現できる世界観にうっとりとさせられる。
タイのシャム王室からの特注を受けた際の見
本織りがいまでも残る。
西陣織の技術を用いて生み出されたファブリックの数々。多彩な織りの表情一つひとつが美しいデザインとなる。
京都御所の北西一帯に、絹織物の町として知られる西陣はある。西陣織の起源は古く5世紀頃まで遡り、平安遷都と共に宮廷の織物を管理する織部司と呼ばれる役所が置かれることで、高級織物として大いに発展した。そんななか、「西陣織 細尾」は江戸元禄年間(1688年)に、本願寺の庇護を受けるかたちで創業。天皇や貴族、徳川将軍家やシャム王室(タイ)などに、手織りの織物を納めてきた。 細尾の取締役で12代目に当たる細尾真孝さん(前頁参照)は、元々はミュージシャンやジュエリーブランドの商品開発者であり、クリエイティブ指向の強い人物。30歳で家業に戻り、豊富なアイデアで、伝統の西陣織の世界に革新をもたらしている。 海外展開事業を託された細尾さんにとっての転機は、ニューヨークからの1本のメールがきっかけだった。2009年、ニューヨークでの見本市に本業の帯を出品すると、それを見た人から帯の技術と素材を使ったテキスタイルを開発したいと依頼されたのである。
送り主は高級ファッションブランドの店内装飾を手掛けるニューヨークの著名建築家、ピーター・マリノ氏。クリスチャン・ディオールの旗艦店の壁面を装飾するファブリックとして、西陣織の技術と素材を用いて、鉄が溶けたような抽象的でコンテンポラリーな柄を作れないかという内容だった。「これまで西陣織は帯や着物などの商品としてしか考えていなかった」と言う細尾さんにとって、西陣織をマテリアルとして捉える発想に目から鱗が落ちたという。さらに、「海外では和柄で差別化をしないと勝てない」とこだわっていたが、むしろ和の要素を取っ払った方が、本来西陣織が持っている技術や素材感が生きてくることに気付かされたのである。
もちろん巨大な壁面用のファブリックを織るには、専用の大きな織機の開発を要されるなど、商品化への道は決して容易ではなかった。しかし、チャレンジの成果もあり、現在では素材としての西陣織は、世界90都市のクリスチャン・ディオールの店舗をはじめ、シャネルやルイヴィトン、グラフの店舗といった、世界のラグジュアリーシーンに欠かせない存在となった。
「新しいことを柔軟に取り込み、自分のものとする強さがあるのが伝統の強み」と細尾さん。壊すつもりで伝統と組み合っても、壊れない強さが伝統にはあると言います。そんな心強い西陣織の伝統に甘んじることなく、「morethan textile」という言葉を標語に、細尾の挑戦は続く。


従来、織機は帯用に32cm幅だが、150cm幅の織機を細尾が独自に開発した。西陣織には20の工程があり、織りはその最後。
家宝の屏風には、特権階級からの特注を受けた際の見本織りの図案が
張られる。天皇家や貴族、徳川将軍家など、錚々たる顔ぶれの顧客を見ると、西陣織が錦織と呼ばれ、いか
に特別な存在であったか分かる。
茶筒 開化堂 ~日本最古の手作り茶筒
茶筒を作り続けるための変化

青海波の美しい柄が刻まれた茶筒。どの茶筒も手の納まりが良く、持った時にしっくりと馴染む。
創業は明治8年(1875年)。文明開化が花開き、世相風俗が大きく変わりつつあった時代、「開化堂」はイギリスから輸入されたブリキを材料に、これまでにない茶筒を世に送り出した。
一つの茶筒が完成するまでに、手作業による130の細かな工程を要する。初代が生み出したその手法は、今も変わることなく受け継がれている。 茶葉を保存する上で大切なのは気密性が高いこと。よって、開かない缶が本来、茶葉には一番いいことになる。しかし、なかなか開かない缶は使い勝手が悪い。だからといって、簡単に開くと空気が入ってしまう。「相反する2つの要素のバランスを取るのがうちの仕事です。手の感覚で覚えるしかないので、そこが本当に難しいところなんですが」。
そう話しながら、6代目の八木隆裕さんが蓋を筒の口の上に合わせて離すと、スーッとゆっくり蓋が滑り落ち始め、一瞬の静寂の後、コトン。何かに操られているかのように蓋が閉まった。まさに手仕事ならではの妙味である。
一切の妥協を許さない職人技による茶筒は、海外の目利きの目に止まり、ロンドンにある紅茶の有名店より販売の打診を受ける。そしてある程度売れ、手応えを掴んだ八木さんは、海外での販路拡大を目指し、パリのメゾン・エ・オブジェなどの見本市に出展。そこで細尾さんなどと出会い、GO ONプロジェクトを立ち上げることになる。



使い込まれて味わい深い色合いになった明治期に作られた茶筒。製法は創業当初から変わらないため、何年経っても修理の対応ができる。まさに一生ものである。
気密性の高さを活かし、コーヒーストッカーなど、現代のライフスタイルに合った商品も展開される。
茶さじは銅製、ブリキ製、真鍮製が揃う。茶筒の素材に合わせて選びたい。
中でも細尾さんの紹介によるデンマーク人デザイナーのトーマス・リッケ氏との出会いは、6代目として伝統を受け継ぐ八木さんの意識を変えるきっかけをもたらすことになった。
リッケ氏は開化堂の象徴である茶筒へのこだわりから一度離れることを提案。テーブルトップを飾るアイテム全てを作ることで、新たなマーケットを切り拓こうと持ちかけたのである。「開化堂としてやっていいことなのか、とても迷った」という八木さん。しかし、初代がどんな気持ちで新しい茶筒を世の中に出したのかを考えてみると、「少しでも新しいことにチャレンジすることは開化堂のDNAではないか」とトライすることに。以後、茶筒を100年作り続けるために、茶筒の技術を活かして様々なことにトライしていくことを軸足に据えるようになった。
開化堂の茶筒は昨年、イギリスのヴィクトリア&アルバート美術館に永久展示されることになった。140年前のものが現在でも作られ、現役として使われていることが評価されたのだ。そのことを裏付けるように、八木さんの元には、100年近く前の古い茶筒の修理依頼が舞い込むという。「修理をしている時が一番幸せ」と笑みを浮かべる八木さんの表情に、職人としての誇りが浮かび上がった。
八木 隆裕 Takahiro Yagi
手作りの茶筒「開化堂」の取締役。得意の英会話を活かして、京都で海外旅行者向けにお土産を販売していたが、開化堂の茶筒が外国人に受け入れられることを目の当たりにして、海外展開を視野に、6代目として家業を継ぐ。趣味は愛車ランチアデルタでのレース。
京金網 金網つじ ~使って分かる本物の味わい
京の美意識を日常に


手仕事によって編み込まれた亀甲模様や菊花模様。日常生活で使う道具とは思えないほどに美しい。ワイヤーアートのようでもある。
コーヒー匙は京都のお土産としても人気の商品。
平安時代にまで遡るといわれる京金網の歴史。銅線を丁寧に一本一本、放射線状に編み込んでいくことで、様々な調理道具を形づくり、京料理の料理人たちに長く愛用されてきた。
創業より35年。高台寺にお店を構える「金網つじ」もまた、料理人をはじめ、表装屋や清水焼の窯元など、いわゆる職人のための道具を作り続けてきた。使い勝手や耐久性を求め、結果として編み上がったその文様はなんとも美しく、まるで芸術品のようである。
金網つじの二代目、辻徹さんは、まだ子供の頃、バブル経済でよその金網屋の多くが、自ら世の中に売り込む姿を目の当たりにしてきた。ところが創業者で父の賢一さんは、以前と変わらず職人からの注文にこだわったまま。いつも経済的に困っている様子の両親に、「なんやねん、こいつら」とうんざりしていたと言います。
しかし、二代目として家業に携わって13年経った今、当時の父親の気持ちが分かるようになったと言います。「正直、楽をして儲けようと思ったら、いくらでもできる。今なら中国などで作ってもらえばいいわけですから。でもそれはできない。なぜなら、次の代がいるから」。
バブルの流れに乗れば簡単だった時代にあえて我を通し、お金にならない道を選んだ初代。そういう時期を経験したからこそ、金網つじにはよそに負けないと自負できる高い技術、つまりこの先もやり続けるための力が、二代目へと受け継がれているのである。 現在、徹さんがこだわるのが、「物を全ての部分で合わせ込む」という考え。海外展開などでは特に顕著だが、現地の生活様式や食文化を自分の目でしっかりと確かめ、理解した上で、必要とされる道具を金網で展開するということ。つまり使い手の生活にこっそりと忍び込もうというのだ。
例えば、台湾で茶托を提案したのは、気候的にも暑く、客人をお茶で迎える文化があることを知ったから。照明の光と金網がテーブルの上に描く影が涼しげなのがうけ、広く現地で受け入れられることになった。これも台湾へ何度も足を運んだからこそ導けた結果。「僕らの道具は使ってもらってなんぼ。だから人を知らないと、国を知らないと、物は作れない」と徹さんは言います。
金網つじの商品は料理人の調理道具をはじめ、茶こしやコーヒー匙など、一つとして食卓の主役になることはない。しかし、例えば、豆腐すくいを使って豆腐を実際にすくってみて欲しい。無表情だった真っ白な豆腐の表面に、花を添えるかのように金網の影が落ちる様を目の当たりにすれば、京都人の美意識が、静かにだが、確かな存在感を持ってそこに潜むことに気付くはずだ。「親父はこれを『脇役の品格』と言います。どんな小物であってもきちっとした物を作る。それが僕らの創作理念なんです」。



紅茶のオレンジ・ペコー用のティー・ストレイナー。細い銀線のみで製作され、上品で繊細な印象。
金網の編み込みの美しさを活かしたランプシェード。明かりを灯した際の金網の線による影が、部屋を妖艶に彩る。
金網つじの定番商品である豆腐すくい。銅線で中央から放射線状に菊の花の模様を編み出す、菊出しという伝統技法が用いられている。
辻 徹 Toru Tsuji
京金網「金網つじ」の二代目。高校卒業後、任された洋服屋を成功させるも、仕入れたものをただ売るだけの仕事に魅力を感じられなくなり、物作りの道へ進むことを決心。夢だったジャマイカ行きを果たした後に、13年前、職人として家業に戻る。
臨済宗大本山建仁寺塔頭 両足院 ~美しい庭園に囲まれた学びの場
現在の芸術が生まれる場所

江戸中期に作庭された書院前庭。茶道の藪内流五代目藪内竹心と両足院10世の雲外東竺の共作と伝えられる。
苔むした枯山水庭園が方丈(本堂)の正面に広がり、書院からは、半夏生に縁取られた池を中心に、京都府の名勝庭園に指定される回遊式庭園を望む。祇園に隣り合わせる広大な建仁寺境内のなか、「両足院」は時間が止まったかのような静寂に包まれる。
ここ両足院は、臨済宗の開祖栄西の弟子で、建仁寺の35世住職だった龍山徳見禅師を祀るために建てられた知足院を前身とする。室町時代中期まで、五山文学の最高峰の寺院の一つで、建仁寺の学問面の中核を担ってきた。
そんな歴史が導くのか、両足院では現在、副住職の伊藤東凌さんを先頭に、文化拠点としての寺院の復興を目指し、様々な試みが進められている。
例えば11月に開催される「京焼今展」もその一つ。琳派をテーマにした京焼の作品展では、ただ展示会場として場を提供するだけでなく、参加作家が創作について東凌さんと坐禅や問答を繰り返し、その末に生まれた作品を展示するというもの。展覧会に先立ち、「多聞会」と呼ぶ勉強会も開き、一般の参加者も交えて、専門家と共に琳派について考える機会も提供された。
両足院が向かう先は、「本物の文化が集い、そして、100年、200年先まで残る、現代の芸術が生まれる場所」と東凌さん。自分たちが両足院に残る長谷川等伯の屏風絵を大切に保存するように、平成の時代の芸術として後世を魅了できるような思想の入った作品を残したいと言う。
その目標を実現すべく、昨年の栄西の800年遠忌を記念して、5年をかけて全92面のふすま絵を描こうという壮大なプロジェクトがすでに動き出している。2016年初めには、創作現場の特別公開も予定されている。歴史の1頁が作られる瞬間を、両足院で目の当たりにしてはいかがだろう。



菱形の飛び石が並ぶ玄関へのアプローチ。
書院から望む池泉回遊式庭園。
両足院では坐禅体験もできる。

両足院副住職の伊藤東凌さん。坐禅体験にヨガを組み合わせるなど、様々なユニークな取り組みを提案・実践している。
臨済宗大本山建仁寺塔頭 両足院
京都市東山区小松町591 建仁寺山内
TEL 075-561-3216
http://www.ryosokuin.com/
「京・焼・今・展」2015 -琳派-
2015年11月1日(日)~3日(火・祝)